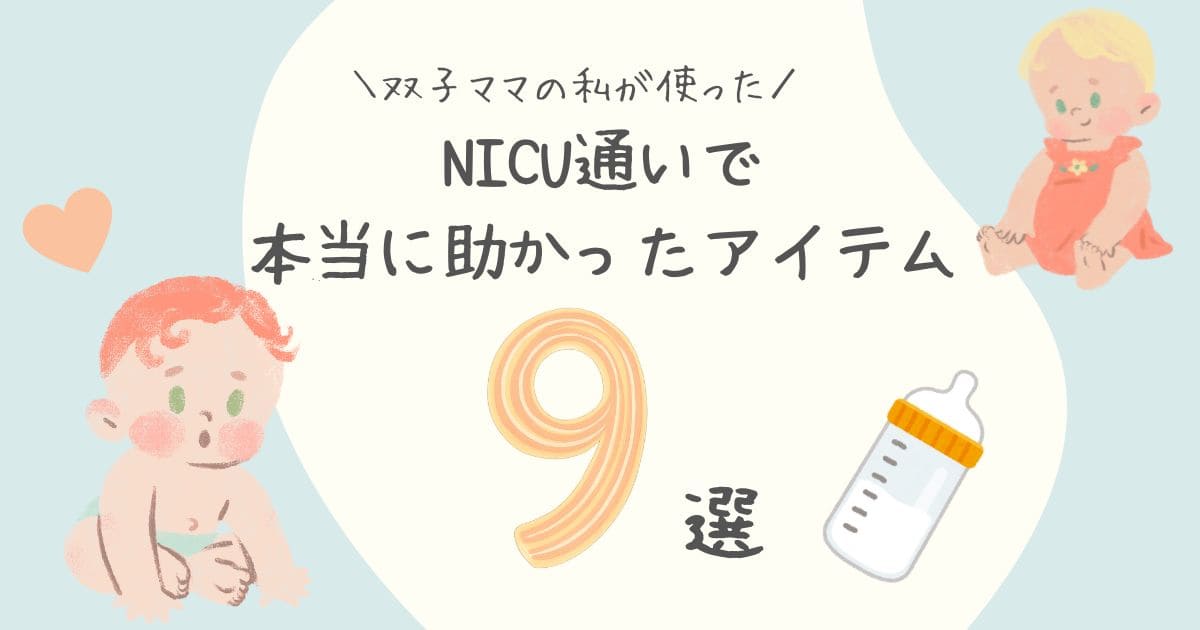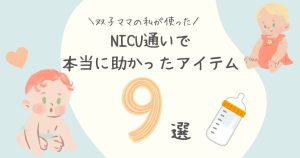11/17が“世界早産児デー”だと、つい先日SNSで知りました。
双子を出産して、我が子たちがNICUで過ごした経験があるからこそ、自然と心に留まったんだと思います。
自分が退院して、いざNICUに通うことになった時、何を準備したらいいんだろう…?”と産後の病室で検索したのを思い出しました。
 なつみ
なつみひとつ前の記事にも書きましたが、34週の妊婦検診で2人の羊水量に差が出始めたので今日から入院してくださいと言われ、その数日後に出産しました。
今日はその時に実際に使っていたグッズや、当時の思い出を少し振り返ってみようと思います。
そんな我が子たちも来月でついに1歳…!保育器に入っていた小さな姿を見ながら早く大きくなって欲しいという想いが形になっていて嬉しいなぁ。
使用していた物の紹介
搾乳機
搾乳機は4つ使用していたので、順に紹介します。
①メデラ シンフォニー
産後すぐ、病院ではメデラの病院専用のシンフォニーという物を使っていました。そのため退院後は同じ物をレンタルしました。
「ダブルポンプセット」というのが、両胸につける搾乳カップが付いたセットになるので、最初のレンタル時はダブルポンプセットを選ぶ必要があります。
そのカップの部分は新品が届く=購入になります。
- メデラ シンフォニーは、日本国内での病院採用率がNo.1
- 母乳を軌道に乗せるためには、病院グレードの搾乳機が最適
- 両胸同時に搾乳できて、効率が良い
最初は1ヶ月レンタルにして、その後また1ヶ月くらい延期したような記憶があります。NICUに通う期間がどれくらいになるか分からないと思うので、最初はレンタルからでいいのかなと思います。
うちは息子が先に生後20日で退院したものの、直母がなかなかできずに2ヶ月くらいは搾乳して飲ませていたので搾乳機は重宝しました。やっと直母できるようになったのは、近所の助産院の産後ケアで助産師さんにみてもらってからでした。
②ピジョン 母乳アシスト さく乳器 電動 handy fit +
シンフォニーのレンタル中に購入する搾乳機を検索して、まずはピジョンの電動の物に決めました。
- 手動より電動が圧倒的にラク
- たまひよ1位などレビューの評価が良かった
- ピジョンというブランドの信頼感
- お出かけにも持っていきやすいコンパクトさ
実際NICUの面会時に持って行き、面会時間の途中での搾乳時に使っていました。



私の時は未発売でした!
③メデラ スイングマキシ電動さく乳機ダブルポンプ+ハンズフリーブラ
両胸の電動さく乳機だけでも使用できますが、ハンズフリーさく乳ブラを付けることで両手が空くという優れものです!
- 両胸用が欲しくなった
- ピジョンは赤ちゃんが吸う力より少し強いという意見もあり、メデラの物が欲しくなった
- ハンズフリーで両手が空くため搾乳しながらスマホを触るなど時間を有効に使えるから
両胸同時搾乳+ハンズフリーが1番ノーストレスです!!
④メデラ スイング・マキシ ハンズフリー電動さく乳器
こちらは両胸同時搾乳+ハンズフリーな上に、わざわざハンズフリーブラを付けなくて済むという最強王者です。



③の進化版という感じ
自分が今付けているブラの中に授乳カップを入れて両胸同時+ハンズフリーで搾乳できるのでこれが1番おすすめ!
しかも③よりパーツが少ない!
私は先に③の購入時に機器をもっていたので、追加でカップのみ購入しました
タイプの違う搾乳機の使い分け方
レンタルしていたシンフォニーの返却後は
*メデラのハンズフリータイプ×2→家用
*ピジョン→NICU面会時用
と使い分けていました。



搾乳機の紹介は長くなりましたが以上です!続いてその他の使用していたアイテムを紹介していきます。
スチーム除菌・乾燥機「ポチット」
私は搾乳そのものよりも搾乳後に搾乳機を分解して洗うっていうのが本当に大変で、、
それを助けてくれた相棒のようなアイテムがポチットでした!
分解、洗う、は夫と交代で頑張りましたが、その後はこのポチットに入れてボタンを押せば除菌、乾燥してくれます。
本当にポチッとがなければ、私の搾乳人生は続かなかったと思います。
深夜も早朝も、何度この子を稼働しただろうか。本当に感謝しているし、いまだに哺乳瓶を洗った時に使っています。
母乳バッグ
カネソンの物を使用していました。
最初はピジョンのものを使っていましたが、カネソンの方がコスパが良かったので途中からはカネソンに変更しました。



ピジョンの物はジップロックみたいな袋なのでそこは簡単!カネソンはテープ式ですが、そんなに使いにくさは感じませんでした。
サイズについては、最初は40~50mlを使用、その後は100ml~150mlを使用していたと思います。
一袋にどれくらいの量を入れて持っていけばいいかは、母乳の出る量と子どもが飲む量で人によって違うと思うので、NICUの看護師さんに聞いたらいいと思います!
保冷剤
少し重さはある保冷剤だけど、衛生上母乳はしっかり冷やして持っていかないと怖いので、頑丈な保冷剤で溶けにくくてよかったです!
保冷バッグ
サーモスなら信頼できる!コーデに合わせやすいように、色はベージュにしました。
ハンドクリーム
NICUに入るまでに手洗いゾーンが2箇所ありました。
そのほか我が子に触れる前やおむつ替えの後も手を洗うので、何かと手を洗うシーンが多く冬のため手荒れしたので、夜寝る時に薬用のハンドクリームを使用していました。
伝えたいこと
通う頻度について
私は産後退院して、翌日から毎日20日間連続で夫と一緒にNICU(途中からはGCU)に通いました。
生後20日で先に息子が退院し娘のみ入院という状況になってからは、1日おき且つ夫と交代で通いました。



双子で1人のみ退院、1人のみ入院となるとはじめての赤ちゃんのお世話+NICU通いの日々になるので、無理ないペースで通っていました。
病院までは電車を使い、ドアTOドアで1時間ほどだったので無理なく通える距離でしたが、なかなかNICUのある病院って限られているので家から少し遠かったりして、通うのが大変なご家庭もあると思います。
それに産後すぐは身体も戻っていない状況だし、NICUに通わない場合は家で過ごすのが一般的な時期です。
なので、頻度については本当に人それぞれ違って当然。
我が子に会いたい気持ち、母乳を届けたい気持ちもありつつ、カラダや心がきつい場合もあると思うので、ありきたりな言葉になりますが、無理ないペースで通ったらいいと思います。
搾乳回数について
新生児の時は3時間おきの授乳と言われるため、搾乳も3時間おき(1日8回)が理想的ではありますが
私は毎日きちんと8回なんてできていませんでした



深夜のアラーム止めたのに寝てしまうこともしょっちゅうでした…
1日5、6回の日が多かったと思いますが、産後11か月の今でも(今はもうミルクメインではありますが)まだ毎日母乳を少しあげられていて、母乳育児を続けることができています。
なので、こちらに関しても無理なく。母乳がきつくなったら辞めることも選択肢に入れつつ自分に優しくしていいと思います。
母乳の量について
搾乳しながらネットで色々調べていると、自分よりもはるかに多く搾乳できている人を見て自分の母乳が少ないんじゃないかなと心配になったこともありました。
でも、私ははじめから完母は目指しておらず、”混合で無理ない範囲で細く長く母乳を飲ませたいな、”という気持ちだったので、無理せず、でも毎日できるだけ搾乳をしよう、という感じで続けていました。
おかげでゆるく長く理想の形で母乳育児ができたかな、と思っています。



産後ケアに行った時、助産師さんからはいつも母乳よく出てるよ!と言ってもらえて安心できました。
写真動画をできるだけ撮ろう
我が子たちが1歳目前になった今、新生児期の写真や動画をみると「あ~この頃の我が子たちにもう1度会いたいな…」と思います。
初産だったので当時は新生児の貴重さが分かりませんでしたが、今写真や動画を見返すと本当に懐かしくて会いたくて仕方ない気持ちになります。
写真も動画も撮っていたけど、もっと撮っていても良かったなと感じるので、できるだけたくさん撮るのがオススメです。
いろんな管に繋がれて保育器に入っている我が子を見るのがつらくてあまり撮影できなかった、でも、今思えば貴重な新生児の姿を残しておけばよかった、という声もネットで見かけたことがあります。
私も娘の方がなかなか何日間もマスクと帽子を外すことができなかったので、早く何にも縛られずに自由に過ごす娘の姿が撮りたい、と思って悲しくて撮れなかった日もありました。
日記を付けるのもおすすめ
毎日病院の帰りの電車の中で、使っている手帳アプリの日記コーナーにその日の子ども達の様子や、出来事や気持ちを付けていました。



日記と一緒に、毎日の搾乳した時間と母乳量、とれた母乳をどう息子と娘に振り分けたかもメモしていました。この日記は妊婦検診の時からはじめていました♪
嬉しいこともきついことも全部そこにメモしておいたので、今見返すと貴重な時期の思い出となっていて宝物になっています。
オススメのYouTube
産前産後”助産師はるかの安産塾”という助産師さんのYouTubeを時々みて参考にしていました。
こちらの助産師さんもお子さんがNICUに入っていた時期があったそうです。
さいごに
我が子たちと離れて暮らした日々があるからこそ、一緒に暮らせる毎日が当たり前じゃないと思い知った期間でした。
家族が元気で一緒に暮らせて何も起きない毎日が嬉しいと感じられるし、過ぎ去った今となれば懐かしくて貴重な時期だったな、といういい思い出に変わっています。



NICUにいる赤ちゃんとそのご家族が幸せでありますように…